
2011年3月12日(土)「スーパーサイエンスデー 最先端と最前線の超一級講座」は広尾学園が行ってきた2010年度キャリア教育の総決算となります。
この日は日本全国から、21世紀の最先端を究めようとする科学者、最前線で開発に挑むエンジニア、宇宙のフロンティアに挑む研究者など、日本の現在と未来を支える方々が広尾学園に結集します。
この24講座が、生徒たちの学問への憧憬の念を育て、科学技術の高みをはるかに見上げる良い機会となることを願っています。
2009年度の講座内容はこちらからどうぞ。
『脳は不思議がいっぱい!!』 自然科学研究機構 生理学研究所 柿木 隆介 先生
ほんの15年程前までは、人間の脳の働きを知るためには心理学的検査と脳波しか方法がありませんでした。動物と違い、人間の脳を検査するためには、けっして傷つけてはいけないからです。しかし、近年の急速な科学技術の進歩により新しい検査方法が次々に開発され、人間の脳の活動(機能)がかなり詳細に分かるようになってきました。今回の講演では、脳波を使った嘘発見器の御紹介、脳の可塑性(機能の柔らかさ)、顔認知研究、痛みと痒みの研究、などについて、最新の研究をわかりやすく御紹介したいと思っています。

『地球規模の創薬:寄生虫からがんまで』 東京大学大学院 生物医化学 北 潔 先生
創薬に関わる人々は「夢追い人」です。この世に人類が生き続ける限り、疾病は無くなりません。そしてその治療に必要な薬剤は私達が自然から見出し、またみずから合成してきたものです。21世紀に入り、世界はますます複雑になり、創薬の対象となる疾病もこれまでの感染症やがんなどに加え、生活習慣病、神経や精神疾患など多岐にわたってきています。このような状況は創薬に携わる研究者にとって真の腕の見せ所であり、また生き甲斐でもあります。グローバルな視点から、今後の創薬について考えてみたいと思います。

『電波で調べる天の川銀河』 鹿児島大学大学院 理工学研究科 半田 利弘 先生
太陽系は天の川銀河と呼ばれる1つの渦巻銀河に属します。そこには1000億個の恒星の他に、その間に広がるガスがあり、星間ガスと呼ばれます。星は星間ガスから生まれ、星間ガスは様々な天体現象に影響されます。その様子は主に電波で観測することではじめてわかりました。これらについて最新の成果を紹介すると共に、直接観測できる量からどのような手法や考えに基づいて、そのような結論が得られるのかまで含めて紹介します。また、太陽系周囲とは大きくようすが変わっている銀河中心付近についても紹介します。

『ロボット技術と未来社会』 千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター 古田 貴之 先生
本講義では、ロボットの仕組みを、例を用いてわかりやすく解説します。ロボットは、センサ、モータ等のアクチュエーターおよびコンピュータ・電子システムの統合機械です。ゆえに関連技術は、人工知能、運動制御、認知手法など多岐に及びます。本講義では「ロボット教習所」をキャッチフレーズに、時には実際のロボットの分解を通じ、また時には図解しながら、前述の構成要素・技術を解説します。いわゆる「座学」だけでは得られない実践的知識の教授を達成するのが狙いです

『南極観測の紹介』 国立極地研究所 第50次南極越冬隊 門倉 昭 先生
地球温暖化の影響で氷が少なくなっている、など、最近は北極についての話題をよく耳にするようになりました。では、南極は? 皆さんは「南極」と聞いて何をイメージするでしょうか? オーロラ? ペンギン? 氷? 地球上でただ1つ国境のない大陸「南極」で、世界中の国々が協力して、または競争して、今何を明らかにしようとしているのか。日本の南極観測隊はどのような活動をしているのか。この講座をきっかけにして、南極のことを、そして私たちが生きている地球のことを、もっと身近に感じてもらえたらと思います。

『夢をつかむ「きぼう」への挑戦』 日本電気(株) 宇宙システム事業部 大塚 聡子 先生
宇宙開発とは何か?世界・日本は宇宙開発において何をしてきたのか?宇宙開発での物作り作業はどのように行われているのか?日本は、宇宙ステーションにどのように関わっているのか?宇宙ロボットとは何か?将来、どのように使われるのか?将来の宇宙開発で、何をすべきなのか?という疑問を、宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」の開発作業のエピソードを交えながら解明していきます。また、宇宙開発を通じて何を実現しようとしているかをご理解頂きたいと思います。

『隕石クレーターをつくってみよう』 日本地球化学会 筑波大学 生命環境科学研究科 丸岡 照幸 先生
地球にはまさにいまのこの瞬間にも宇宙空間から物質が飛来し続けています。その中にはときどき大きなものがあり、燃え尽きずに地表へ到達します。この地表に到達したものがいん石です。さらにその中には地球の環境を変えてしまうほどの大きなものもあり、このようないん石衝突が起こるときにはクレーターができます。世界最大級のチュクシュルーブ・クレータを紹介し、それができるときに何がおきたのかについてお話したいと思います。恐竜の絶滅にはこのイベントが関わっています。

『海底温泉でやんわりと暮らすには?』 海洋研究開発機構 和辻 智郎 先生
光の届かない深海では植物が育たないので、そのとても大きな空間に動物と微生物だけが住んでいます。そして、深海底のほとんどは静寂な砂漠のように生き物を寄せ付けない世界が広がっています。しかしながら、砂漠にもオアシスがあるように深海底にも生命にあふれた場所があります。それが300℃以上もの温泉が湧き出る「熱水噴出域」です。そのような環境に住む動物はどのようにして暮らしているのでしょうか。その驚きの暮らしぶりを研究手法を交えて紹介いたします。

『地震の波で地球の中を見る』 海洋研究開発機構 田中 聡 先生
大きな地震を感じるといくつになっても怖いものです。だけど、そんな地震のエネルギーは、はるか地球の裏まで伝わって、地球の神秘を私たちに届けてくれます。遠くから伝わってくる地震のささやきはとても小さいので、私たちは地震計という機械を使います。100年前は1トンもあった地震計はすっかり軽くなって、今は山の上や海の底まで地震計を持っていくことができます。これはまさに、地球の中を知るための携帯聴診器なのです。さあ、今日は地震計から聞き出した地球の知られざる姿の一端をご紹介しましょう。

『雪と凍土と気候 陸域寒冷圏の長い変化と変動』 海洋研究開発機構 斉藤 和之 先生
雪や凍土は地球の陸地の半分近くで起きている現象です.東京でも雪が降るし,霜柱は最も身近な凍土現象です.一方,両極圏やヒマラヤなどには地面の下にずっと凍った層,永久凍土があります.でも永久凍土は「永久」ではありません.地球の歴史に沿って見れば気候や地形の変化に伴って永久凍土も伸張・消滅を繰り返しています.それが今の環境変動の中でどう変化しているのか,その変化にどんな含意があるのか.それを観測やモデルや解析を通して解き明かそうとする,その現場を伝えようと思います.

『未来のエネルギー源“核融合”』 核融合科学研究所 中村 幸男 先生
昨今、地球環境あるいはエネルギー問題が叫ばれているが、その問題点の紹介をすると共に、それを解決するための最先端科学である核融合研究について紹介したい。核融合炉は化石燃料に頼らず、炭酸ガスを放出しない未来のエネルギー源として注目されている。その核融合炉を実現するためには、超高温のプラズマを限られた空間に定常的に閉じ込めて維持しなければならない。プラズマと核融合についての科学的な基礎を説明すると共に、新たなエネルギー革命を起こす核融合炉開発について紹介する。

『タイムドメインとスピーカー』 タイムドメイン社 由井啓之 先生
タイムドメイン 心のオーディオ:理論の概要と製品 Yoshii9,MINI,lightの試聴。ベンチャー企業:会社発足と、開発発展の経過。心のオーディオ:今までのオーディオとの違い:音楽、自然、癒し。創造のメカニズム:改善開発では無く、どうすれば創造出来るか。知識より知恵:考える事が大切、何かでオンリーワンとなる。
(参考資料:オーディオマニアとしても知られるビル・ゲイツ氏は、そのスピーカーを試聴して「信じられない」を連発したという。自分の家の7000万円をかけたオーディオシステムより良い音だ、と。(『ビル・ゲイツを驚愕させた由井啓之のスピーカー作り』より
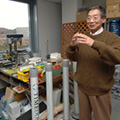
『アインシュタインの遺産 〜重力波を求めて〜』 法政大学理工学部 創生科学科 佐藤 修一 先生
光による伝統的な天文学の幕開けから400年、近代天文学は様々な波長の「光」を用いて発展を遂げてきました.一方で全く新しい観測手段による宇宙の観測も始まろうとしています.アインシュタインがその相対性理論のなかで予言した「時空のさざなみ」、重力波(じゅうりょくは)です.たとえば巨大な質量を持つ天体同士が衝突・合体するとき,時空間の歪みが波動(重力波)として放射され,宇宙空間を光速度で伝わっていきます.この想像を絶するほど微かな宇宙のささやきを捉えようとする世界の研究者たちの試みと今後の展望について紹介します

『素粒子論的宇宙論への誘い:暗黒物質』 東京大学 宇宙線研究所 伊藤 英男 先生
貴方は宇宙の内容物についてどれだけの知識がありますか?恒星や銀河はもちろん、ブラックホールや中性子星、そして地球のような惑星、彗星や小惑星、はたまた星間ガスなどと答えるかもしれません。それら全ては我々人類が実験によって生み出すことが出来る既知の物質で形成されています。ところが近年、様々な観測から既知の物質というのは宇宙の内容物のたった4%に過ぎないことが分かってきました。残りの76%とは一体何なのでしょうか?本講座では、その中の約20%を占める暗黒物質と呼ばれる未知の物質について動画等を用いて簡単に説明します。そしてその基礎となる素粒子物理学についても紹介します。

『フタバスズキリュウの発見と白亜紀の窓』 フタバスズキリュウ発見者 鈴木 直 先生
今から40年ほど前、日本から恐竜など中生代に栄えた大型は虫類化石が発見されるとは予想もされなかった時代がありました。日本各地から恐竜化石が知られるようになった昨今を予見するできごとがフタバスズキリュウの発見だったのです。本日はこのフタバスズキリュウの発見・発掘や、産出した双葉層群という地層(8900万年~8500万年前)からのぞき見得る“白亜紀の窓“のお話をしたいと思います。

『生物の「なぜ?」を探るフィールドサイエンス』 国立科学博物館 濱尾 章二 先生
実験室で分析を行い、生物体のメカニズムを明らかにすることだけが生物学ではない。「なぜ、鳥は渡りを行うのか?」「なぜ、一部の鳥は一夫多妻になるのか?」このような生態や行動についての機能や進化に関する疑問を解くのも生物学の一分野である。かつては「多分○○のためだろう」としか語られることがなかったこのような疑問にも、野外での観察や実験から答えが与えられつつある。野外での生物学は標本や記載的な知識の収集にとどまるものではない。「なぜ?」に挑むフィールドサイエンスの世界を紹介する。
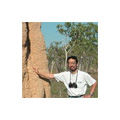
『世界に溢れる数学の威力と魅力』 明治大学 理工学部 数学科 『大学への数学』著者 長岡 亮介 先生
数学は、受験のために必要だと思われ、そのために、他人より早く正確に解くための勉強が大切だと信じている人が多いようですが、本当は、数学ほど、習得することが容易で、しかも楽しいものは、なかなかないのではないか、おそらく若いうちは見つけることが出来ないのではないか、と私は考えています。 しかも現代社会は、もっとも身近なものまで数学の力なしには何もできないほど、ありとあらゆる場面で数学が活躍しています。 そのことが見えにくいのは、折角「数学」を学ぶ機会に恵まれながら計算やドリルのような「数学もどき」の反復練習だけに終ってしまう人が多いからではないかと思います。 講義では数学を学ぶとはどういうことか、やや高い立場から、しかし、進んだ知識を仮定しないでお話し出来ればと考えています。

『遊びと数学』 埼玉大学 経済学部 『分数ができない大学生』(共編著) 岡部 恒治 先生
今回の学習指導要領で、高校数学の科目「数学活用」の項に「遊びと数学」が入りました。数学は、物理学や化学はもちろんのこと、ときにはギャンブルなどのあらゆる分野と関連して発展してきました。この講義では、実際に遊びを取り入れて(といってもパズルですが)、数学を考えます。こうすることで数学の奥深さを味わってください。
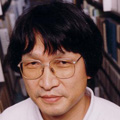
『ダイヤモンドの科学:宝石から超伝導まで』 NIMS超伝導材料センター 高野 義彦先生
宝石の王様として知られる、あの透明で綺麗なダイヤモンド。実は、黄色やブルーのダイヤモンドもごく希に産出します。そして、真っ黒なダイヤモンドの中には、金属のように電気が流れ、低温で電気抵抗が完全にゼロになる超伝導を示すものまであります。ダイヤモンドの科学を宝石から半導体、超伝導にわたりお話しします。

『ノーベル賞と日本人』 物質・材料研究機構 元日経サイエンス編集長 科学ジャーナリスト 餌取 章男 先生
湯川秀樹博士が日本人としてはじめてノーベル賞を受賞したのは1949年(昭和24年)です。その後50年の間に湯川博士を含めて自然科学分野で5人の受賞者が出ていますが、ちょうど10年に1人の割合でした。ところが2000年代になると、2000年から2010年までの間に10人の受賞者が生まれました。毎年1人の計算です。これは日本の科学が世界一流になり、世界中の人々がそれを認めたということを物語っています。それは日本のノーベル賞受賞者は一体どんな研究をしたのでしょうか。

『スーパーコンピュータ「京」って何だろう?』 理化学研究所 横川 三津夫 先生
スーパーコンピュータを知っていますか?最新の技術で作られる科学技術計算向けの高性能コンピュータのことで、あまり知られていませんが、天気予報、超高層ビルや自動車の設計など、私たちの身の回りのものにも多く利用されています。 今、理化学研究所では世界最高レベルの計算能力(1秒間に1京回の計算を行う。現在、一般に使われているスーパーコンピュータの約100倍の速さ!)をもつスーパーコンピュータ「京(けい)」の開発が行われています。本講義では「京」の仕組みについてお話しします。

『小惑星探査機「はやぶさ」の挑戦』 宇宙航空研究開発機構 西山 和孝 先生
小惑星探査機「はやぶさ」は2003年5月に地球を旅立ち、2005年9月に地球から3億kmかなたの小惑星イトカワに到達し、大きな科学観測成果を上げました。イトカワへの着陸とサンプル採取後のトラブルにより、7週間もの通信途絶を経験しましたが、奇跡的に復旧し3年延期して地球帰還を目指すことにしました。2009年秋にはエンジントラブルのため帰還が絶望視されましたがこれも克服し、2010年6月にオーストラリアの砂漠でサンプルの入ったカプセルの回収に成功しました。

『ナノカーボンの世界』 産業技術総合研究所 針谷 喜久雄 先生
ナノメートル(10のマイナス9乗メートル)の大きさを持った、炭素の作る新物質、サッカーボール型分子「フラーレン」やナノメートルの直径を持つ「ナノ チューブ」を扱います。サッカーボール型分子やカーボンナノチューブの紙模型を作って、ナノカーボン系の不思議を体験します。講師の論文は、2010年、 グラフェンに関するノーベル物理学賞受賞論文において引用され紹介されました。

『加速器で迫る宇宙の謎 この世界は対称か?』 KEK高エネルギー加速器研究機構 中山 浩幸 先生
こんなクイズがあります。「遠い星の宇宙人との交信に成功した。物を運ぶことはできず、情報のやり取りのみができる。このような状況で、宇宙人に左右の概念を伝えることはできるだろうか?」このクイズに答えるヒントは、「対称性の破れ」というキーワードです。茨城県つくば市にある我々の加速器実験施設によって実証され、2008年の日本人ノーベル物理学賞受賞につながった、「小林・益川理論とCP対称性の破れ」について、わかりやすくお話しします。研究者の普段の生活についても、少しだけご紹介します。

